構成障害の判断材料として、コース立方体組み合わせテストを行うことがあります。今回、コース立方体テストを行う際の実施方法と注意点についてまとめていきたいと思います。
目次
line登録もよろしくお願いします
ブログには書けない裏話、更新通知、友だち限定情報などを配信(完全無料)!まずは友だち追加を♪臨床を助けるnote
訪問指導でお悩みの方、自信がない方⇨訪問指導で在宅復帰と住宅改修を成功させるコツ
前頭葉障害に対するリハビリテーション
⇨遂行機能障害リハ(GMT、自己教示法、問題解決訓練、TPM)
高次脳機能障害でアウェアネスどう評価し、どう高めるか
⇨効果を高める!高次脳機能障害のリハビリテーション-アウェアネス(病識・認識メタ認知)をどう評価し、どう高めるか-
注意課題のプリント課題
⇨注意障害プリント課題データ(文字選択、計算、図形)
橋損傷のリハビリテーション
⇨橋損傷のリハビリテーション(脳画像からの評価項目選定や治療戦略立案)
脳画像の達人へ
⇨新人・学生さんが脳画像の達人に近づくために!脳部位と機能局在、脳のつながりから考える画像の診方!
リハビリテーションと運動学習
⇨リハビリテーションと運動学習!保持や転移(汎化)を促す方法!
認知症リハビリテーション
⇨認知症における作業活動の重要性と課題設定、評価の支援とポイント〜脳機能面も考慮して意欲と運動学習を促し、ADL・IADLを促す方法〜
起立と着座動作のリハビリテーション
⇨起立と着座動作が上手くいかないの原因分析〜誰でも理解できる筋活動とバイオメカニクス、脳機能との関連性も踏まえながら〜
感覚障害のリハビリテーション
⇨感覚障害のリハビリテーション!脳科学と伝統的リハを融合させる考え方と実践方法〜随意性の促進も見据えて〜!
スポンサードサーチ
高次脳機能障害についてのおすすめ記事
- 高次脳機能障害で動作の順序の間違いやペースに問題がある場合のリハビリテーション
- 高次脳機能障害のアウェアネス低下に対するアプローチ
- ADL場面における高次脳機能障害の問題に対するアプローチ!大まかな戦略の枠組みを知る!
- 視床損傷(出血、梗塞)で高次脳機能障害(行為の抑制障害)が生じる理由と症状の特徴!
- 中脳レベルの脳画像と、損傷部位から予測される高次脳機能障害!
- 基本動作、ADLの観察評価!高次脳機能障害の現れ方!
- 高次脳機能障害と作業遂行上のエラーに対する支援とアプローチの例
- 更衣動作評価で観察するべき視点!高次脳機能障害を中心として!
- 高次脳機能障害による計算障害のリハビリテーション
- 高次脳機能障害の、数に関する障害の知識と評価
- 純粋失書はなぜ生じるのか?メカニズムを解説!
- 純粋失読はなぜ生じるのか?メカニズムを解説!
- 右半球損傷と認知コミュニケーション障害
- 超皮質性感覚失語症の特徴とコミュニケーション促進の関わり方
- 発語失行(失構音)の特徴とコミュニケーション促進のための関わり方
- 超皮質性運動失語症の特徴とコミュニケーション促進のための関わり方
- ウェルニッケ失語症の特徴と症状、コミュニケーション改善のための関わり方
- 伝導失語症の特徴、症状とコミュニケーション改善のための関わり方
- 空間関係(前後左右、図と地の判別など)の障害がある場合のリハビリテーション
- ブローカ失語のコミュニケーション能力の特徴と改善のための関わり方
- 全失語の特徴と症状、コミュニケーション改善のための関わり方
- 健忘性失語症(失名詞)の特徴、症状とコミュニケーション改善のための関わり方
- 触覚失認の概要と評価、リハビリテーションの考え方
- 相貌失認の概要と評価、リハビリテーションとその対応
- 注意障害の観察評価!BAADの概要と評価方法、結果の解釈!
- 注意機能障害は歩行に影響する?注意機能と移動能力、転倒の関係を解説!
- 注意機能と言語機能!注意障害はコミュニケーションにどう影響するか?
- 注意障害に対するプリント課題素材集(ATP:Attention Process Trainingを参考に)
- 注意障害に対するトランプを用いたアプローチ(APTを参考に)
- 内包の損傷で記憶障害が生じる理由!内包膝部の脳画像の見方!
- 視床損傷(出血、梗塞)で失語が起こる理由と症状の特徴!
- 視床の損傷(出血、梗塞)で記憶障害が起きる理由!脳画像の見方!
- 半側空間無視の勉強会スライド〜能動的注意と受動的注意の視点から〜
- 半側空間無視における受動的注意には電気刺激療法が効果的?!
- 記憶障害の詳しすぎる評価法やリハビリテーションアプローチを紹介
- 失行をくまなく評価し、リハビリテーションアプローチにつなげる知識と方法!
- 前頭葉損傷(遂行機能障害)に対する評価と作業療法、リハビリテーションアプローチ
- ゲルストマン症候群に対してはどのようなリハビリ(作業療法)を行うのか
スポンサードサーチ
構成障害について
構成障害のポイントを以下に挙げていきます。
・個々の運動の失行はなく、操作の空間的形態が侵される行為障害
・形態の構成が選択的に障害される
・課題の遂行結果における失敗、不正確さが目立つ
・この症状そのものが日常生活を障害するものではないが、その原因とされる半側空間無視、知能の低下、分析能力・計画性の低下などが問題となることが多い
・立体的なものを紙面上に書くことができない。模写をするとき手本に重ねたり、部分的にくっつけて描いたりする現象が見られる。
・誤りに気付いても訂正不可能であることが多い
普段から、図案を書くことや見ることに慣れている人であれば、検査を行う中でうまく書けないときに、それを認識できるかどうかも障害を見極めるポイントになります。
スポンサードサーチ
コース立方体組み合わせテストの実施の目的
・一般知能を検査する
*満6才以上の常能者、ろう児難聴児童生徒、神経心理分野で使用される
スポンサードサーチ
コース立方体組み合わせテストの実施方法
所要時間:20〜50分(平均35分)
練習:
①練習用模倣図と必要立方体4個とを離して平らに置き、提示する。
②検査者は4個の立方体を手に取り、1つ1つが皆同じこと、色々な色がついている事を指摘し、理解させる(色の名前は言ってはいけない)。
③検査者が組み立てる(4つに区切って並べ方を教えない)。
④対象者の練習ができれば、理解したとみなして本検査に入る。
*練習が不可なら3回まで行い、それでも不可であれば本検査を受ける事ができないが、念のため検査を行う事もある。
本検査:
①4つの立方体を右側に与えておく。
②正面に図面を伏せておく。
③「用意始め」の合図で、模倣図を見せ、作業開始と同時にストップウォッチを押し、並べ、完成できるまでの時間を測定する。
④制限時間ない内に間違っていた場合、「この辺がおかしいですね」と指摘する。
⑤次の課題を行うときには、立方体をバラバラにする。
*続けて2テスト失敗すれば、それ以降の課題は不可能と判断し、テスト終了となる。
テスト1〜9まで:立方体4個
テスト10〜14まで:立方体9個
テスト14〜17まで:立方体16個
スポンサードサーチ
コース立方体組み合わせテスト実施上の工夫点や注意点
・最初のブロックの説明では、「色々な色のついた立方体があり、すべて同じ形です。これら4個のブロックを使って、この図と同じ絵柄を作ってください。これら4個のブロックで1つの絵ができます」とオリエンテーションを行う。
・終了時には「できましたか」と確認をとる。
・1回のテストが終わるごとにブロックをバラバラにする。
・間違った箇所があれば、その部分を示し本人に修正してもらう(4個のブロックを分けて間違いを指摘するのではなく、「ここらへんがおかしいですね」というように1つの物体として考えてもらう)。
・色の識別ができるかどうかをオリエンテーション時に確認する。
・時間だけでなく、どのように作成したかの過程についても観察を行う。
・検査中の反応(注意の維持など)も観察しておく。
呼吸療法認定士の資格を取りたい方は必見
呼吸療法認定士の資格勉強は隙間時間にするのがコツです。呼吸療法認定士 eラーニング講座
スキマ時間勉強ならリハノメ
PTOTSTのためのセミナー動画が見られます。各分野のスペシャリストが登壇しているので、最新の知見を学びながら臨床に即活かす事が可能です。
セミナーあるあるですが、、、メモ取りに夢中になり聞き逃してしまった。
なんてことはなくなります。何度でも見返す事が可能だからです。
高額なセミナー料+交通費、昼食代を支払うよりも、スキマ時間を見つけて勉強できる「リハノメ」を試してみるのも良いのではないかと思います。
臨床で差をつける人は皆隠れて努力していますよ。
PT.OT.STのための総合オンラインセミナー『リハノメ』
PTOTSTが今より給料を上げる具体的方法
転職サイト利用のメリット
何らかの理由で転職をお考えの方に、管理人の経験を元に転職サイトの利用のメリットを説明します。転職活動をする上で、大変なこととして、、、
仕事をしながら転職活動(求人情報)を探すのは手間がかかる
この一点に集約されるのではないでしょうか?(他にもあるかもしれませんが)
管理人は転職サイトを利用して現在の職場に転職しました。
コーディネーターの方とは主に電話やLINEを通してのコミュニケーションを中心として自分の求める条件に合う求人情報を探してもらいました。
日々臨床業務をこなしながら、パソコンやスマホで求人情報を探すというのは手間ですし、疲れます。
そういう意味では、転職サイト利用のメリットは大きいと考えています。
転職サイト利用のデメリット
デメリットとしては、転職サイトを通して転職すると、転職先の病院や施設は紹介料(転職者の年収の20-30%)を支払うことです。これがなぜデメリットかというと、転職時の給与交渉において、給与を上げにくいということに繋がります。
それでも、病院や施設側が欲しいと思える人材である場合、給与交渉は行いやすくなるはずです。
そういった意味でも、紹介してもらった病院や施設のリハビリ科がどのような現状で、どのような人材が欲しいのかといった情報が、自分の持つ強みを活かせるかといった視点で転職活動を進めていくことが大切になります。
転職サイトは複数登録することも必要
転職サイトは複数登録しておくことが重要になるかもしれません。それは、転職サイトによって求人情報の数に違いが生じることがあるからです。
せっかく転職サイトを利用するのであれば、できるだけ数多くの求人情報の中から自分の条件にあった求人情報を探せる方が良いはずです。
その分複数のコーディネーターの方と話をする必要がありますが、自分のこれからのキャリアや人生を形作っていく上では必要なことになります。
また、コーディネーターの方も人間ですから、それぞれ特性があります。
自分に合う合わないと言うこともありますから、そういった意味でも複数サイトの登録は大切かもしれません。
とにかく行動(登録)!管理人も登録経験あり!転職サイトのご紹介!
ネット検索にある転職サイトの求人情報は表面上の情報です。最新のものもあれば古い情報もあり、非公開情報もあります。
各病院や施設は、全ての求人情報サイトに登録する訳ではないので、複数登録する事で より多くの求人情報に触れる事ができます。
管理人の経験上ですが、まずは興味本位で登録するのもありかなと思います。
行動力が足りない方も、話を聞いているうちに動く勇気と行動力が湧いてくることもあります。
転職理由は人それぞれですが、満足できる転職になるように願っています。
管理人の転職経験については以下の記事を参照してください。
「作業療法士になるには」「なった後のキャリア形成」、「働きがい、給与、転職、仕事の本音」まるわかり辞典
転職サイト一覧(求人情報(非公開情報を含む)を見るには各転職サイトに移動し、無料登録する必要があります)
①PT/OT/STの転職紹介なら【マイナビコメディカル】
②理学療法士/作業療法士専門の転職支援サービス【PTOTキャリアナビ】
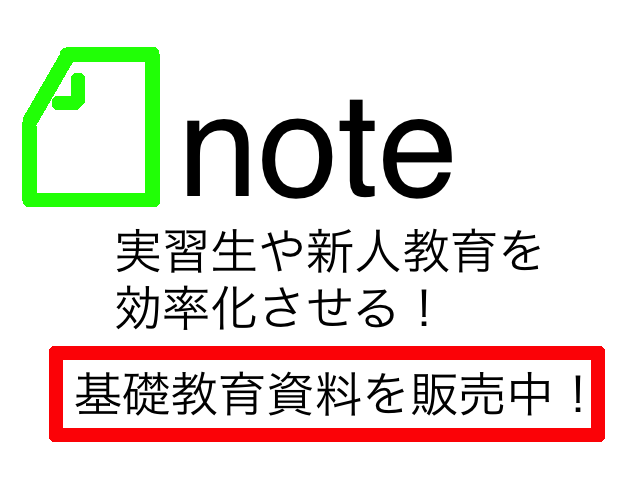

Pingback: コース立方体テスト(目的、方法、IQ算出、結果の解釈)と、頭頂葉・後頭葉、前頭葉領域障害による取り組み方の違い | 自分でできるボディワーク