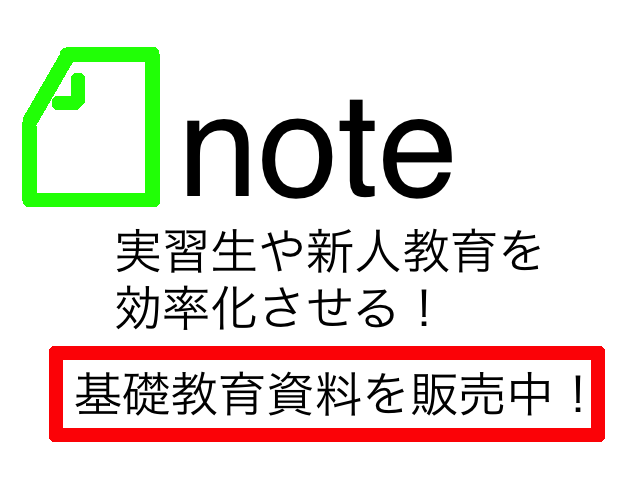運動維持困難やペーシング障害の評価法をご存知でしょうか。今回、運動維持困難やペーシング障害に対する評価法をまとめていきたいと思います。
スポンサードサーチ
目次
高次脳機能障害を勉強する上でオススメの書籍
スポンサードサーチ
運動維持困難の概要と臨床場面での例
運動維持困難とは、
・目を閉じる
・舌を出す
・口を開ける
などの動作を一定の間持続させることができない状態をさします。
運動維持困難の定義では、運度麻痺によりそれらの動作が持続できないことは含まれません。
なお、「目を閉じる」「舌を出す」といった2つの運動を維持することができないことに関しては、「同時失行」と呼ばれることがあります。
運動維持困難では、麻痺側だけでなく、非麻痺側においても運動の維持が難しくなることが特徴です。
そのため、両手をバンザイするような両側課題において、両手をすぐに下ろしてしまうことが観察されます(*運動麻痺の場合は麻痺側のみ腕が落ちてきます)。
臨床場面で、運動維持困難がみられやすい場面は、いくつか考えられます。
・感覚検査ですぐに目を開けてしまう
・視野検査で目を動かさないように指示されてもすぐに動かしてしまう
このようなことでは検査で精査ができないので、とても困ったことになります。
感覚検査では、顔にタオルを被せるなどで対応可能ですが、視野検査に関しては困ったものです。
【スポンサーリンク】
スポンサードサーチ
運動維持困難とペーシングの障害は共存していることが多い?
運動維持困難とペーシングの障害(一定のリズムで動作を行ったり、ゆっくりと動作を行えない状態)と同時に症状がみられることが多いとも言われています。
2つの症状が合わさった全般的な作業行動の特徴は、粗雑・粗動・性急といったかたちで現れる。
たとえば、車椅子からベッドへ移るまでの一連の動作において、各動作の安定性や完了をみないまま、次々に動作を行ってしまう。
また、毛筆経験が長い人でも毛筆を行うと、毛筆に特徴的な流れや止め、はらいなどのリズムがなくなり、とても経験者とは思えない”下手な字”となる。
岩崎テル子他 「標準作業療法学 専門分野 作業療法評価学」医学書院 2005
私自身としては同時に組み合わさっている印象はなかったのですが、本を開いて確認をしているとこのような記述があり興味深かったため掲載しました。
スポンサードサーチ
運動維持困難の評価法は?どのような検査を行うのか
Joyntらによる詳細な評価ツールもあるようですが、詳しくは書籍「高次脳機能障害学」を参照してください。
臨床場面では、セラピストが対象者に指示を出し、その運動が維持可能かを見ていく方法をとります。
運動としては、
・目を閉じる
・目を開けて舌を出す
・目を開けて口を開く
の運動を20秒維持することが可能かを評価します。
また、目を閉じる動作の維持は15秒以下で異常、
目を閉じて舌を出す動作の維持は20秒以下で異常とする考え方もあるようです。
なお、上肢の運動維持困難の有無を評価するには、前途しましたがバンザイ動作をの維持が可能かを見ていきます。
運動麻痺があっても、運動維持困難は非麻痺側に起こるとされていますから、非麻痺側の挙上を維持できるかを評価するようにします。
スポンサードサーチ
運動維持困難に対するリハビリテーションの考え方
運動維持困難が認められる場合、基本動作やADLの動作学習が進みにくいことが指摘されています。
そこで、ひとつの方法として考えられるのが自己教示法を用いた訓練方法です。
これは、「高次脳機能障害を有する左片麻痺患者への安定した立位保持獲得への取り組み」を参考にしています。
自己教示法とは、簡単に言うと、自分に言い聞かせるようにするアプローチ方法です。
自己教示法は、元々多動児に対して行われていたものを、前頭葉損傷者に適応したものです。通常内的に行われる自己モニタリング過程を代償する内的補償の1つとなります。
内言による行動調整を重視したLuria(1981)の理論を基盤としたもので,これを用いた訓練では,課題遂行中の患者にその実行手順を逐次明瞭に外言化させることから始まり,訓練経過ともに徐々に外言化を弱め,内言化を導いていく.
柴崎 光世「前頭葉機能障害の認知リハビリテーション」明星大学心理学年報 2012,No.30,23―40
自己教示法では、他の場面への般化も起こりやすいとされています。
【スポンサーリンク】
Aldermanetal.(1995)は,自己モニタリング訓練による訓練効果は比較的ゆっくりとあらわれるものの,TOOTSやレスポンスコストといった行動療法的手法と違って,他の環境への訓練効果の般化が起こりやすいと述べている。
柴崎 光世「前頭葉機能障害の認知リハビリテーション」明星大学心理学年報 2012,No.30,23―40
詳しくは、以下の記事を参照してください。
自己教示法による遂行機能障害のリハビリ
方法ですが、維持したい運動課題に対して、「自分で◯秒数えながら運動を継続して行う」というように自分で数えながら課題を維持させます。
例えば、座位でバランスを要しない状態での運動維持課題から、立位でバランスを要する運動維持課題など、難易度を段階的に調整することも考えられるでしょう。
呼吸療法認定士の資格を取りたい方は必見
呼吸療法認定士の資格勉強は隙間時間にするのがコツです。呼吸療法認定士 eラーニング講座
スキマ時間勉強ならリハノメ
PTOTSTのためのセミナー動画が見られます。各分野のスペシャリストが登壇しているので、最新の知見を学びながら臨床に即活かす事が可能です。
セミナーあるあるですが、、、メモ取りに夢中になり聞き逃してしまった。
なんてことはなくなります。何度でも見返す事が可能だからです。
高額なセミナー料+交通費、昼食代を支払うよりも、スキマ時間を見つけて勉強できる「リハノメ」を試してみるのも良いのではないかと思います。
臨床で差をつける人は皆隠れて努力していますよ。
PT.OT.STのための総合オンラインセミナー『リハノメ』
PTOTSTが今より給料を上げる具体的方法
転職サイト利用のメリット
何らかの理由で転職をお考えの方に、管理人の経験を元に転職サイトの利用のメリットを説明します。転職活動をする上で、大変なこととして、、、
仕事をしながら転職活動(求人情報)を探すのは手間がかかる
この一点に集約されるのではないでしょうか?(他にもあるかもしれませんが)
管理人は転職サイトを利用して現在の職場に転職しました。
コーディネーターの方とは主に電話やLINEを通してのコミュニケーションを中心として自分の求める条件に合う求人情報を探してもらいました。
日々臨床業務をこなしながら、パソコンやスマホで求人情報を探すというのは手間ですし、疲れます。
そういう意味では、転職サイト利用のメリットは大きいと考えています。
転職サイト利用のデメリット
デメリットとしては、転職サイトを通して転職すると、転職先の病院や施設は紹介料(転職者の年収の20-30%)を支払うことです。これがなぜデメリットかというと、転職時の給与交渉において、給与を上げにくいということに繋がります。
それでも、病院や施設側が欲しいと思える人材である場合、給与交渉は行いやすくなるはずです。
そういった意味でも、紹介してもらった病院や施設のリハビリ科がどのような現状で、どのような人材が欲しいのかといった情報が、自分の持つ強みを活かせるかといった視点で転職活動を進めていくことが大切になります。
転職サイトは複数登録することも必要
転職サイトは複数登録しておくことが重要になるかもしれません。それは、転職サイトによって求人情報の数に違いが生じることがあるからです。
せっかく転職サイトを利用するのであれば、できるだけ数多くの求人情報の中から自分の条件にあった求人情報を探せる方が良いはずです。
その分複数のコーディネーターの方と話をする必要がありますが、自分のこれからのキャリアや人生を形作っていく上では必要なことになります。
また、コーディネーターの方も人間ですから、それぞれ特性があります。
自分に合う合わないと言うこともありますから、そういった意味でも複数サイトの登録は大切かもしれません。
とにかく行動(登録)!管理人も登録経験あり!転職サイトのご紹介!
ネット検索にある転職サイトの求人情報は表面上の情報です。最新のものもあれば古い情報もあり、非公開情報もあります。
各病院や施設は、全ての求人情報サイトに登録する訳ではないので、複数登録する事で より多くの求人情報に触れる事ができます。
管理人の経験上ですが、まずは興味本位で登録するのもありかなと思います。
行動力が足りない方も、話を聞いているうちに動く勇気と行動力が湧いてくることもあります。
転職理由は人それぞれですが、満足できる転職になるように願っています。
管理人の転職経験については以下の記事を参照してください。
「作業療法士になるには」「なった後のキャリア形成」、「働きがい、給与、転職、仕事の本音」まるわかり辞典
転職サイト一覧(求人情報(非公開情報を含む)を見るには各転職サイトに移動し、無料登録する必要があります)
①PT/OT/STの転職紹介なら【マイナビコメディカル】
②理学療法士/作業療法士専門の転職支援サービス【PTOTキャリアナビ】