痛覚検査は臨床であまり馴染みがないかもしれません。しかし、痛覚を感じることができるということは、リスク管理を行う上では非常に大切なことになります。今回、温痛覚検査の目的や方法、伝導路や神経解剖学的なことについてまとめていきたいと思います。
目次
line登録もよろしくお願いします
ブログには書けない裏話、更新通知、友だち限定情報などを配信(完全無料)!まずは友だち追加を♪臨床を助けるnote
訪問指導でお悩みの方、自信がない方⇨訪問指導で在宅復帰と住宅改修を成功させるコツ
前頭葉障害に対するリハビリテーション
⇨遂行機能障害リハ(GMT、自己教示法、問題解決訓練、TPM)
高次脳機能障害でアウェアネスどう評価し、どう高めるか
⇨効果を高める!高次脳機能障害のリハビリテーション-アウェアネス(病識・認識メタ認知)をどう評価し、どう高めるか-
注意課題のプリント課題
⇨注意障害プリント課題データ(文字選択、計算、図形)
橋損傷のリハビリテーション
⇨橋損傷のリハビリテーション(脳画像からの評価項目選定や治療戦略立案)
脳画像の達人へ
⇨新人・学生さんが脳画像の達人に近づくために!脳部位と機能局在、脳のつながりから考える画像の診方!
リハビリテーションと運動学習
⇨リハビリテーションと運動学習!保持や転移(汎化)を促す方法!
認知症リハビリテーション
⇨認知症における作業活動の重要性と課題設定、評価の支援とポイント〜脳機能面も考慮して意欲と運動学習を促し、ADL・IADLを促す方法〜
起立と着座動作のリハビリテーション
⇨起立と着座動作が上手くいかないの原因分析〜誰でも理解できる筋活動とバイオメカニクス、脳機能との関連性も踏まえながら〜
感覚障害のリハビリテーション
⇨感覚障害のリハビリテーション!脳科学と伝統的リハを融合させる考え方と実践方法〜随意性の促進も見据えて〜!
温痛覚検査の目的や方法、伝導路や神経解剖学的なこと!
スポンサードサーチ
感覚の神経解剖学やリハビリテーションを学びたい方にオススメの書籍
スポンサードサーチ
感覚についてのおすすめ記事
- 各感覚検査のカットオフや判定基準はあるのか!
- デルマトームと感覚障害!デルマトームを使用するのはどんな時か!
- 運動・位置覚検査の目的や方法、伝導路や神経解剖学的なこと!
- 触覚検査の目的や方法、伝導路や神経解剖学的なこと!
- 感覚障害はないが指の運動障害がある!前骨間神経症状の原因と評価の考え方!
- リハビリテーションと感覚入力!感覚が入るとどのような変化があるのか!
- 感覚障害の評価とリハビリテーションアプローチ!効果を出すために必要なこと!
- 頸髄症の評価バッテリー!日本整形外科学会頚髄症治療成績判定基準(JOAスコア)の概要と評価方法、結果の解釈!
- 頚椎症における神経根症状と脊髄症状の違いと各特徴!リハビリで知っておきたい事!
- 手の甲(手背)にしびれがある!橈骨(後骨間)神経症状の原因と評価の考え方
- 手のしびれと手根管症候群!正中神経症状の原因と評価の考え方!
- 腕や指の小指側にしびれがある!尺骨神経症状の原因と評価の考え方!
- アクティブタッチとパッシブタッチにおける脳活性化部位の違い
スポンサードサーチ
温痛覚について
体性感覚は表在感覚と深部感覚に分かれますが、温痛覚(+触覚、圧覚)は表在感覚に分類されます。
温痛覚はリスク管理にとって絶対に必要な感覚です。
例えば、温度覚が脱失していればお風呂に入る時にお湯が熱過ぎたら火傷をしてしまいますし、痛覚が脱失していれば手を何かにぶつけた時に気づかずに処置が遅れてしまうかもしれません。
このように、温痛覚の検査をすることには非常に意義があります。
温痛覚に機能低下があれば、対象者にはリスク管理についての教育・指導を行う必要があります。
何かがあってからでは遅いので、まずは検査を行い、状態に応じたアプローチが必要になります。
触覚に関しては以下の記事も参照してください。
触覚検査の目的や方法、伝導路や神経解剖学的なこと!
スポンサードサーチ
温痛覚の伝導路
温痛覚の伝導路は、外側脊髄視床路になります。
温度覚と痛覚は同じ伝導路を通っています。
温痛覚は、刺激を受けた感覚受容器から、脊髄で交叉し、反対側の側索を通って大脳まで情報が伝達されます。
具体的には、
1次ニューロン:
自由神経終末→脊髄後根→後角
2次ニューロン:
反対側へ交叉→延髄→橋(脊髄毛帯)→中脳→視床
3次ニューロン:
大脳皮質(体性感覚野)
というような流れになります。
スポンサードサーチ
痛みを感じるメカニズム
痛覚を起こす刺激を侵害刺激と呼び、痛覚に関連する感覚受容器を侵害受容器と呼びます。
侵害受容器は皮膚、皮下組織、筋肉、関節、骨膜、血管周囲に分布する自由神経終末だと言われています。
侵害受容器の繊維には複数の種類があります。Aδ繊維(グループⅢ)は有髄で直径1〜5μm、伝導速度4〜30m/s、C繊維(グループⅣ)は無髄で直径0.3〜1.5μm、伝導速度0.4〜2m/sなどがあります。
Aδ繊維は、強い圧迫などの機械的な侵害刺激に応じる繊維で、機械的侵害受容繊維と呼ばれています。
C繊維は機械的のみならず化学的や熱による侵害刺激に応じ、多様式侵害受容繊維と呼ばれています。
機械的侵害受容繊維は強い機械的刺激に反応しますが、皮膚が傷ついている場合や長時間加温された場合は46℃以上の熱刺激にも反応することもあります。
スポンサードサーチ
温度を感じるメカニズム
温度覚は温覚と冷覚に分かれます。四肢体幹の温・冷受容器はAδ繊維とC繊維の自由神経終末によって伝えられます。
皮膚の上には温点(温覚のみを引き起こす)や冷点(冷覚のみを引き起こす)と呼ばれる直径1㎜以下の小領域があります。
一般的には温点よりも冷点の方が分布密度が高く、そのため温度覚の障害では温覚が冷覚よりも先に、広範囲で障害されます。
スポンサードサーチ
温痛覚検査の目的
・リスク管理のため
・2次的な障害の可能性の有無を予測するため
スポンサードサーチ
痛覚検査の方法
検査肢位:背臥位
必要物品:針、記録用紙
①非麻痺側(健側)にてデモンストレーションを行います。
②触れたら「はい」と答えて(手を挙げて)もらいます。
③触れた箇所を指差してもらいます。
④左右との比較を行います(非麻痺側を10とした時に麻痺側はどの程度か)
スポンサードサーチ
痛覚検査の注意点
・検査実施前に、自分で痛みの加え具合を確認しておく必要があります。
・開眼にてデモンストレーションを行い、理解しているか確認後、閉眼にて行います。
・暗示や誘導を行わないように注意します。
・ときどき刺激を加えないなど、本当に知覚できているかを確認するようにします。
・脱失や重度鈍磨の対象者の場合、針での刺激でなくつまむなど方法を変えて行ってみます。また、段階付けとして開眼状態で痛み刺激を感じることが可能かも評価します。
・対象者の発言(刺激の感じ方)を具体的に記載するようにします。
・温度覚に関しては、痛覚と同じ経路を通るので、痛覚検査で代用することがほとんどだと思います。
呼吸療法認定士の資格を取りたい方は必見
呼吸療法認定士の資格勉強は隙間時間にするのがコツです。呼吸療法認定士 eラーニング講座
スキマ時間勉強ならリハノメ
PTOTSTのためのセミナー動画が見られます。各分野のスペシャリストが登壇しているので、最新の知見を学びながら臨床に即活かす事が可能です。
セミナーあるあるですが、、、メモ取りに夢中になり聞き逃してしまった。
なんてことはなくなります。何度でも見返す事が可能だからです。
高額なセミナー料+交通費、昼食代を支払うよりも、スキマ時間を見つけて勉強できる「リハノメ」を試してみるのも良いのではないかと思います。
臨床で差をつける人は皆隠れて努力していますよ。
PT.OT.STのための総合オンラインセミナー『リハノメ』
PTOTSTが今より給料を上げる具体的方法
転職サイト利用のメリット
何らかの理由で転職をお考えの方に、管理人の経験を元に転職サイトの利用のメリットを説明します。転職活動をする上で、大変なこととして、、、
仕事をしながら転職活動(求人情報)を探すのは手間がかかる
この一点に集約されるのではないでしょうか?(他にもあるかもしれませんが)
管理人は転職サイトを利用して現在の職場に転職しました。
コーディネーターの方とは主に電話やLINEを通してのコミュニケーションを中心として自分の求める条件に合う求人情報を探してもらいました。
日々臨床業務をこなしながら、パソコンやスマホで求人情報を探すというのは手間ですし、疲れます。
そういう意味では、転職サイト利用のメリットは大きいと考えています。
転職サイト利用のデメリット
デメリットとしては、転職サイトを通して転職すると、転職先の病院や施設は紹介料(転職者の年収の20-30%)を支払うことです。これがなぜデメリットかというと、転職時の給与交渉において、給与を上げにくいということに繋がります。
それでも、病院や施設側が欲しいと思える人材である場合、給与交渉は行いやすくなるはずです。
そういった意味でも、紹介してもらった病院や施設のリハビリ科がどのような現状で、どのような人材が欲しいのかといった情報が、自分の持つ強みを活かせるかといった視点で転職活動を進めていくことが大切になります。
転職サイトは複数登録することも必要
転職サイトは複数登録しておくことが重要になるかもしれません。それは、転職サイトによって求人情報の数に違いが生じることがあるからです。
せっかく転職サイトを利用するのであれば、できるだけ数多くの求人情報の中から自分の条件にあった求人情報を探せる方が良いはずです。
その分複数のコーディネーターの方と話をする必要がありますが、自分のこれからのキャリアや人生を形作っていく上では必要なことになります。
また、コーディネーターの方も人間ですから、それぞれ特性があります。
自分に合う合わないと言うこともありますから、そういった意味でも複数サイトの登録は大切かもしれません。
とにかく行動(登録)!管理人も登録経験あり!転職サイトのご紹介!
ネット検索にある転職サイトの求人情報は表面上の情報です。最新のものもあれば古い情報もあり、非公開情報もあります。
各病院や施設は、全ての求人情報サイトに登録する訳ではないので、複数登録する事で より多くの求人情報に触れる事ができます。
管理人の経験上ですが、まずは興味本位で登録するのもありかなと思います。
行動力が足りない方も、話を聞いているうちに動く勇気と行動力が湧いてくることもあります。
転職理由は人それぞれですが、満足できる転職になるように願っています。
管理人の転職経験については以下の記事を参照してください。
「作業療法士になるには」「なった後のキャリア形成」、「働きがい、給与、転職、仕事の本音」まるわかり辞典
転職サイト一覧(求人情報(非公開情報を含む)を見るには各転職サイトに移動し、無料登録する必要があります)
①PT/OT/STの転職紹介なら【マイナビコメディカル】
②理学療法士/作業療法士専門の転職支援サービス【PTOTキャリアナビ】


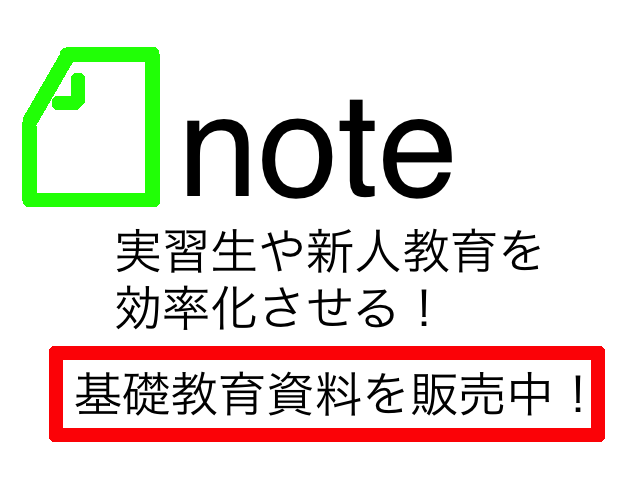

Pingback: 運動・位置覚検査の目的や方法、伝導路や神経解剖学的なこと! | PTOTST学生のための学習塾